5歳は「じぶんでやる」が合言葉。園や家庭で挑戦の場面が増え、成功の喜びも、うまくいかない悔しさも行き来します。そんな揺れる心に寄り添い、もう一歩踏み出す背中をそっと押すのが絵本のちから。今回は、挑戦と安心のバランスを整えつつ、親子のやり取りで自己肯定感を育てる絵本を、司書×母の視点でピックアップします。
「できた!」が自信になる|5歳の心を支える絵本6選
小さな成功が積み重なると、子どもは自分に期待できるようになります。一方で、うまくいかない瞬間も確実に増える年頃。安心できる展開と予測しやすい言葉運びの絵本を選ぶと、「やってみたい→できた!」の橋がかかります。
5歳が感じる「できる」と「むずかしい」のあいだに寄り添う絵本
5歳は「ひとりでやってみたい」と思う気持ちが芽ばえる一方で、「むずかしい」「できない」と感じる場面も増えていく時期です。挑戦と失敗をくり返すなかで、少しずつ自信の芽が育っていきます。そんな揺れ動く心をそっと見守り、背中を押してくれる絵本を選びました。
『はじめてのおつかい』(作:筒井頼子/絵:林明子/福音館書店)
はじめてのミッションに挑むみいちゃんの緊張と達成感が、細やかな表情から伝わってきます。読み終えたあとに「今日はどんな小さな“できた”があった?」と話すと、日常の中の自信を見つけやすくなります。
『できるかな? あたまからつまさきまで』(作:エリック・カール/訳:工藤直子/偕成社)
動物のまねっこをしながら体を動かすうちに、自然と「できた」という気持ちが育ちます。一緒にポーズをとりながら読むと、笑顔が広がるひとときに。寝る前は小さめの動きで、穏やかなテンポがおすすめです。
『めっきらもっきら どおん どん』(作:長谷川摂子/絵:ふりやなな/福音館書店)
ことばのリズムに誘われて進む、ふしぎな冒険のお話です。少し怖くて、でもおもしろい――そんな揺れを味わうことが、気持ちの切り替えの練習になります。読み終えたら、深呼吸をひとつ。
落ち込んだときは気分転換!5歳の自信をはぐくむ絵本
小さな成功を積み重ねることで、子どもの中に「できた」の記憶が増えていきます。失敗や不安もその一部として受けとめ、笑いながら次の一歩へ進む――そんな心の余白をくれる絵本を集めました。
『ぼちぼちいこか』(作:マイク・セイラー/絵:ロバート・グロスマン/訳:今江祥智/偕成社)
やってみたけれど、うまくいかない日もある。そんなときに「まあ、ぼちぼちいこか」と笑いをくれる一冊です。失敗を軽やかに受けとめるユーモアが、明日への気持ちをやわらかくします。
『ちいさな きいろい かさ』(作:もりひさし/絵:にしまきかやこ/金の星社)
女の子が黄色い傘で動物たちを傘に入れてあげる雨の日の物語。はじめての散歩の高揚が描かれます。通園や外出の前に読むのも◎です。雨の日が特別に感じられる一冊。
『おおきくなるっていうことは』(作:中川ひろたか/絵:村上康成/童心社)
服が小さくなる、新しい歯がはえる、そして自分より小さな人にやさしくなれる――「大きくなったなあ」と思えるできごとを挙げていく一冊。日々の成長を、うれしさとちょっぴりの誇らしさで包んでくれる絵本です。
失敗してもだいじょうぶ|ポジティブなメッセージを伝える絵本6選
つまずきを描く物語は、悔しさを言語化し、再挑戦へ気持ちを運ぶ手すりになります。起承転結が明快で、読後に笑顔が戻るタイプを選ぶと、翌日の一歩につながります。
失敗から立ち上がる主人公に勇気をもらえる絵本
失敗を経験することは、成長の通過点でもあります。うまくいかない瞬間にどう向き合うか――その姿勢を絵本から学べることがあります。がっかりした気持ちも笑いに変えながら、「もう一度やってみよう」と思える物語を紹介します。
『かっても まけても いいんだよ』(著:オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ/訳:垣内磯子/主婦の友社)
勝ってうれしい、負けてくやしい。そんな感情をまるごと受け止めるあたたかな構図です。「くやしかったね」と共感してから読むと、子どもが自分の気持ちを言葉にしやすくなります。
『あつかったら ぬげばいい』(作・絵:ヨシタケシンスケ/白泉社)
「○○だったら、○○すればいい」というくり返しの展開が、発想の切り替えを楽しく教えてくれます。家庭でも“わが家版フレーズ”を作ると、前向きな会話が広がります。
『MR.MEN LITTLE MISS もう いちど やって みよう(Try Again)』(編:講談社/著:サンリオ/著:ロジャー・ハーグリーブス/講談社)
転んでも何度でも挑戦する主人公の姿が、自然と笑顔を引き出します。ユーモラスな展開でレジリエンス(立ち直る力)を体感できる絵本です。短い文章構成で、朝の読み聞かせにもぴったりですよ。
5歳の「がんばる気持ち」を包み込む絵本
子どもは、大人のひとことに大きな影響を受けます。「だいじょうぶ」「見てたよ」といった声かけが、次の挑戦を支える力になります。ここでは、結果よりも「あなた」を認める温かい言葉が印象的な絵本を紹介します。
『きみのことが だいすき』(作・絵:いぬいさえこ/パイ インターナショナル)
結果よりも“あなた”そのものを受け入れる視点が、心の土台を温めてくれます。読み終えたあとに「今日はどんな言葉がうれしかった?」とたずねると、気持ちを言葉にする練習にもなります。
『あなたの すてきな ところはね』(作:玉置 永吉/絵:えがしら みちこ/KADOKAWA)
「あなたのすてきなところはね」から始まる語りかけで、子どもの日々の姿をやさしく見つめる一冊。がんばった日もうまくいかなかった日も、“そのままのあなた”を大切にするまなざしが伝わります。
『きみは たいせつ』(作:クリスチャン・ロビンソン/訳:横山和江/BL出版)
“どんな君もたいせつ”というメッセージが、読後に安心を残します。失敗してもまた挑戦したくなる――そんな優しい勇気をくれる一冊です。
いろんな気持ちに気が付く|「友だち」や「家族」との関わりを描く絵本6選
友だちや家族との関係は、自分の価値を映す鏡。違いを面白がったり、ぶつかった後に修復したり――社会的な成長が進む5歳に、感情を整理できる作品を。
友だちとの気持ちを分かち合うお話
5歳になると、友だちとの関わりの中で「うれしい」「くやしい」「ごめんね」といった感情を強く経験します。関係のぶつかりや誤解も、心を育てる大切なきっかけです。ここでは、気持ちを伝え合うことの難しさと温かさを描いた絵本を紹介します。
『くれよんのくろくん』(作・絵:なかやみわ/童心社)
役割を見失っていたくろくんが、仲間と協力して大きな絵を完成させる物語です。仲間外れの痛みを通して、“いっしょに描く喜び”にたどりつきます。作品づくりや共同制作の前に読むと効果的です。
『ともだちや』(作:内田麟太郎/絵:降矢なな/偕成社)
「ともだちってなんだろう?」という問いを、きつねとおおかみの会話を通して深める名作です。読み終えたあと、「仲直りの言葉」を親子で一つ選んでおくと、日常でも使いやすくなります。
『けんかのきもち』(文:柴田愛子/絵:伊藤秀男/ポプラ社/)
けんかの後に生まれるもやもやを、自分のことばで整理していく過程が描かれます。感情の名前を見つけ、関係を結び直す力を育ててくれる一冊です。クラスや園でのトラブル対応にもおすすめです。
家族のぬくもりを感じる絵本
家族とのやりとりは、子どもにとって「自分は愛されている」という確信を育てる時間です。うまくいかない日があっても、ぬくもりのある言葉やふれあいが心を支えます。ここでは、日常の中にある優しさを思い出させてくれる絵本を紹介します。
『うまれてきてくれてありがとう』(作:にしもとよう/絵:黒井健/童心社)
「あなたはかけがえのない存在」という言葉がくり返され、読むたびに安心が広がります。寝る前に一章句だけ復唱すると、子どもの心にやわらかな余韻が残ります。
『おかあさん だいすきだよ』(作・絵:みやにしたつや/金の星社)
伝え方ひとつで、気持ちの届き方が変わることに気づかせてくれるお話です。読みながら「どんな言葉ならうれしい?」とたずねると、相手の立場で考える力が育ちます。
『だいじょうぶ だいじょうぶ』(作・絵:いとうひろし/講談社)
おじいちゃんの「だいじょうぶ」という言葉が、不安を受け止めて前に進む勇気をくれます。家族で“お守りフレーズ”を決めておくと、日常の安心スイッチになります。
「わたしっていいな」|自分を好きになるきっかけをくれる絵本6選
比べない優しさが、自己肯定感の芽を守ります。外見や性格の違いをユーモアや対話で肯定する作品を選ぶと、日常の“自分らしさ”も見つけやすいですよ。
コンプレックスをやさしく包むストーリー
「人とちがう」ことに気づきはじめるとき、子どもは自分をどう見ていいか戸惑うものです。そんな気持ちをやさしく受けとめ、自分の個性を好きになれるよう導いてくれる絵本を紹介します。違いを比べるのではなく、面白がる視点を伝えてくれます。
『みえるとか みえないとか』(作:ヨシタケシンスケ/相談:伊藤亜紗/アリス館)
世界の見え方は人によってちがう――そんな当たり前を、軽やかな対話で伝えます。読み終えたあとに「わたしとあなたの“ちがい・おもしろいところ”」をひとつずつ交換すると、気づきが深まります。
『フンころがさず』(作:大塚健太/絵:高畠純/KADOKAWA)
“変だね”を“いいね”に変えるユーモアが光る作品です。短いくり返しが楽しく、自分らしさを誇る気持ちをそっと残します。読後に「うちの家族のいいね!」を言い合うのもおすすめです。
『わたしは あかねこ』(作:サトシン/絵:西村敏雄/文溪堂)
周囲と違う“色”を自分の魅力として受け入れていく物語です。読み終えたあとに、「好きなこと」や「得意なこと」を家族で一言ずつ共有すると、前向きな自己理解につながります。
好きなことが「わたしらしさ」になる絵本
好きなことに夢中になる時間は、子どもが自分を好きになる入口です。誰かと違っていても「これがわたし」と言える気持ちが育つと、自信の芯がしなやかに太くなります。ここでは、“好き”を肯定してくれる絵本を紹介します。
『ジュリアンはマーメイド』(作・絵:ジェシカ・ラブ/訳:横山和江/サウザンブックス社)
好きな姿を表現するジュリアンの気持ちを、大人が温かく受け止める物語です。自分の“好き”を誰かに伝える勇気を応援してくれます。読後に「いま応援してほしいこと」を語り合うのも素敵です。
『ぼくのニセモノをつくるには』(作・絵:ヨシタケシンスケ/ブロンズ新社)
“じぶんらしさって何だろう”をユーモアを交えて問いかける一冊です。親子で「わたしのニセモノ仕様書」を作ってみると、内面の特徴が見えてきます。思考の整理にもおすすめです。
『じぶんだけの いろ―いろいろさがしたカメレオンのはなし』(作:レオ・レオニ/訳:谷川俊太郎/好学社/)
比べる気持ちから離れ、自分の色を見つけていく物語です。短い文章と印象的な絵が、自己受容の感覚をすっと伝えます。古くから読み継がれる名作。
「読む時間が好き」になる|日常のなかの自己肯定感
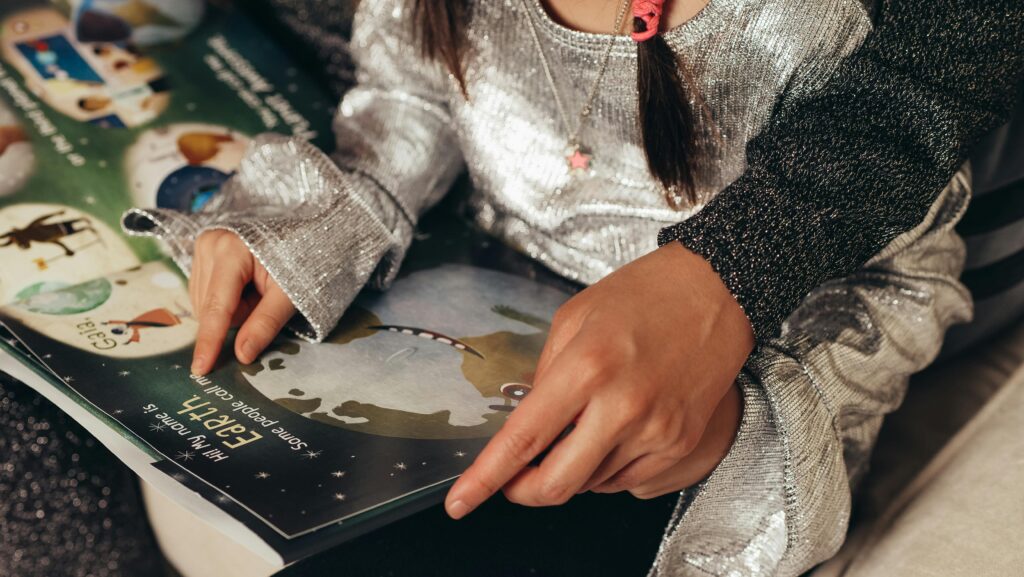
一日の終わりに同じ調子で読む“安心の儀式”があると、心の体温を整えやすくなります。お気に入りを何度も読むことは、自然な読み方です。記憶の中に“安心の回路”のような感覚が少しずつ積み重なっていきます。
読み聞かせを「安心の時間」にするコツ
読み聞かせは、上手に読むことよりも“安心のリズム”を共有する時間。少し落ち着いた声色と、いつもよりゆっくりめのテンポを意識すると、親子ともに呼吸が合わせやすくなります。ページをめくる間(ま)を一定に保つと、物語に浸りやすくなりますよ。
同じ本をくり返すことも大切です。前半は子がめくり、後半は親がめくるなど、役割にちいさなリズムをつけると、安心感と主体性のバランスがとりやすくなります。
読み終えたら質問を重ねるより、「ここ好きだったね」などの一言で気持ちをそっと結びます。
子どもと一緒に選ぶ絵本のたのしみ
絵本を選ぶ時間も、親子の大切なコミュニケーションです。本棚は、表紙を見せる面と背表紙を並べる面を組み合わせると、見やすさと探しやすさの両方が生まれます。お気に入りは、子どもの目線の高さに置くのがおすすめです。
選ぶときの合言葉は「今日はどんな気分?」。うれしい、くやしい、つかれた――そんな気分から選ぶ習慣が、自己理解の第一歩になります。親の“推し絵本”を一冊そっと混ぜてもよいですが、読む順番は子どもに委ねるのがコツ。選ぶ楽しさを守ることが、自信の芽をそっと育む助けになります。
5歳の自己肯定感を育む絵本|まとめ
5歳は「できた」と「むずかしい」の間を行き来しながら、自信の芽を育てていく時期です。絵本は、その揺れる気持ちを受け止め、「わたしはわたしでいい」と感じられる場所にもなります。挑戦を励まし、失敗を笑いに変え、好きなことを見つける。──そんな時間が、安心と意欲を少しずつ積み重ねていく助けになります。
あとがき
子どもは失敗も成功も、同じくらい大切に覚えています。だから、読書の時間は“どちらの気持ちも置いておける場所”に。いつまでも手元に置いておきたい、そんな絵本に出会えますように。



