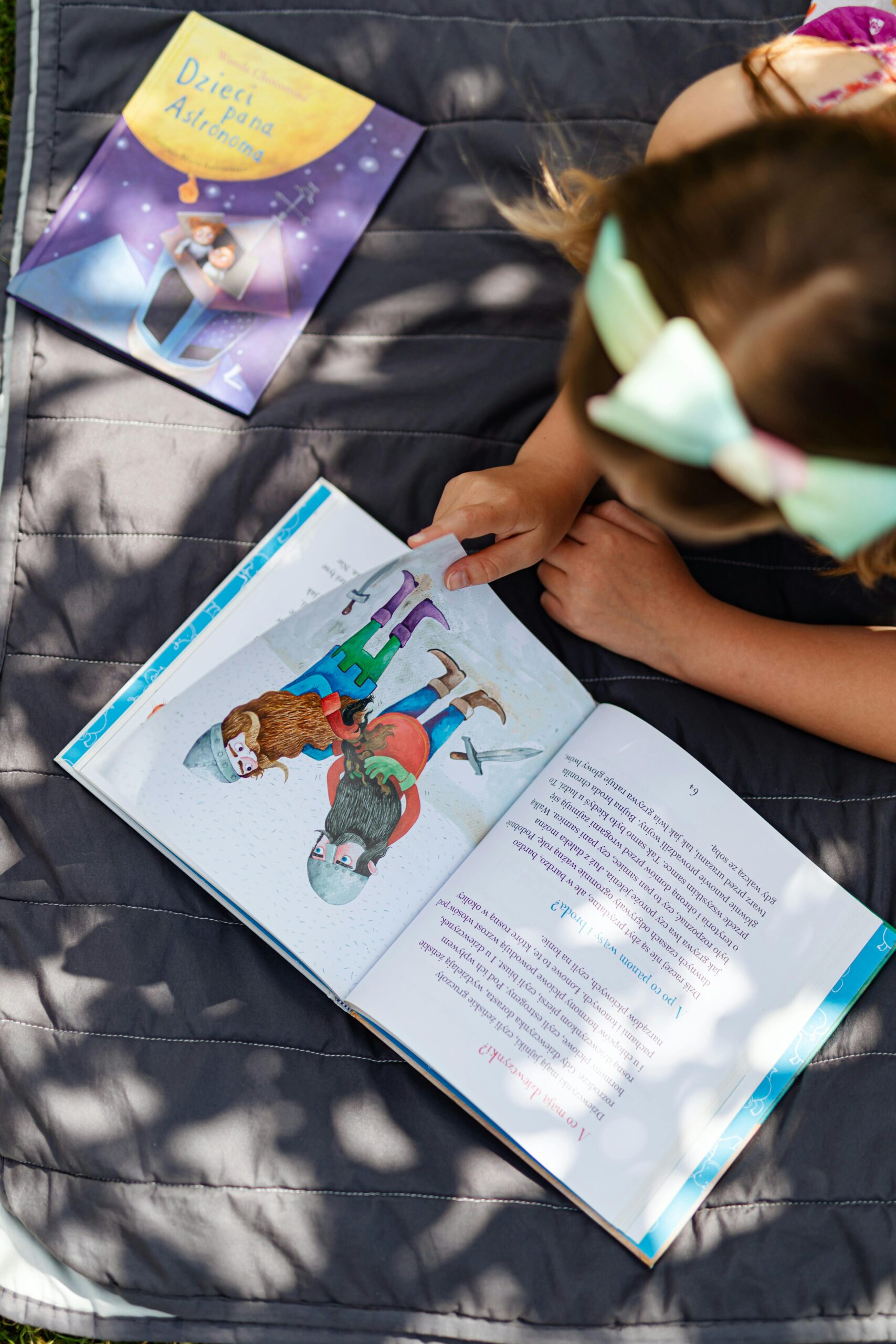子どもの自己肯定感をどう育てればよいのか、迷っていませんか。
今回は、年齢に合わせて“自分はこれでいい”と思える力をそっと支える絵本をまとめました。
児童書専門の司書として、日々の小さな自信につながる物語を選んでいます。
自己肯定感を育む過程で絵本が果たす役割
自己肯定感とは「自分は大切にされている」と感じられる気持ちのことです。
子どもの成長に欠かせないこの感覚は、日々の体験のなかで少しずつ育まれていきます。
絵本はその入り口となる存在です。
ここでは、自己肯定感を育む過程で絵本が果たす役割を見ていきます。
挑戦する物語が心の栄養になる理由
挑戦する主人公の姿にふれると、子どもは「自分もやってみようかな」と思う瞬間があります。
うまくできるかどうかは問題ではなく、その気持ちが芽生えること自体が大切な一歩です。
物語のなかで小さな達成をともに喜ぶ経験は、自信の芽を育てる種となります。
失敗する場面があっても、その後に少しずつ希望が描かれていくことが多いため、「またやってみよう」という思いを安心して受け取ることができるのです。
共感や自己受容を促すストーリーの力
泣いたり迷ったりする主人公に出会うと、子どもは自分の気持ちと重ねることがあります。
弱さや葛藤が描かれた物語は、「そんな自分でも大丈夫」と感じられるきっかけになります。
登場人物の姿がそっと寄り添うように映り、不安な心を和らげたり、気持ちを整理する小さな手がかりをくれたりするかもしれません。
そうした体験の積み重ねが、安心や自己受容を支える力へとつながっていきます。
子どもの自己肯定感を高める絵本の選び方
子どもの発達段階にあわせて絵本を選ぶと、安心や自信、そして自分らしさを少しずつ育むことにつながります。
ここからは、年齢ごとに意識したい視点を整理します。
0歳〜2歳:愛情や安心感を実感できる表現があるか
この時期に大切なのは「自分は愛されている」という実感。
やさしい繰り返しやリズム、抱っこしながら読むスキンシップが、子どもの心にぬくもりを残します。
言葉がまだ理解できなくても、声の調子や表情から伝わる安心感が心の土台になっていきます。
3歳〜5歳:葛藤や挑戦を描き、自立を後押しする物語か
園生活が始まると、多くの子どもは「自分でやりたい」気持ちと、うまくいかない現実のあいだで揺れ動きます。
挑戦する主人公や失敗から立ち直る物語は、自分の姿を重ねやすいもの。
読んでいるうちに「またやってみよう」と思えるきっかけになり、小さな自立を支える力になります。
📘くやしい経験や失敗が続いたときの“立ち直り方”を絵本でたどるなら、失敗から立ち直る力を育む絵本も参考になります。自己肯定感の育ち方を、日常の場面に重ねやすくなります。
6歳以降:多様性や自分らしさを前向きに肯定しているか
小学校に入ると、友だちとの関わりの中で違いに気づく場面が増えていきます。
絵本を選ぶときは「多様性を認め合うこと」や「自分らしさを肯定すること」をテーマにした作品を意識するとよいでしょう。
こうした物語は、子どもが人との関わりを広げるときの支えになります。
📘 友だちとの距離感でモヤモヤが溜まりやすい時期には、友だち関係のモヤモヤに寄り添う絵本も参考になります。
親の視点:つまずいても立ち直る力を育む物語か
努力や失敗を温かく描いた物語は、大人が子どもにどう声をかけるかのヒントになります。
結果よりも「がんばったね」と過程を認めることができれば、子どもは安心して挑戦を続けられますね。
親子で共感を分かち合う時間は、立ち直る力を支える小さな積み重ねになっていきます。
📘「やってみよう」を支える物語は、自己肯定感の土台ともつながります。挑戦する気持ちを育てる絵本でも紹介しています。
【年齢別】自己肯定感を高める・育む絵本リスト15選

子どもの発達に合わせて絵本を選ぶことは、安心や自信の芽を育てる大切なきっかけになります。
ここでは年齢ごとにおすすめの作品を紹介します。
どれも長く心に寄り添ってくれる絵本です。
📘年齢ごとに視点を変えるなら、3歳向けや5歳向けの記事も参考になります。
0歳〜2歳:安心感を実感できる絵本5選
言葉の響きや色のぬくもりが、そのまま心を包むように届く時期です。
抱っこしながらページをめくるひとときに、安心とやさしさを感じられる絵本を集めました。
※本ページにはアフィリエイト広告が含まれます。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
📘感情の受けとめ方に注目するなら、イヤイヤ期の絵本も近いテーマです。
3歳〜5歳:自信と自立を応援する絵本5選
自分でやってみたい気持ちが芽生える時期。
挑戦や失敗を温かく描いた物語は「自分もできる」という自信につながります。
📘小さな前進が“自信”につながる流れは、【自信を高める絵本】の記事でさらにくわしく紹介しています。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
6歳以降:個性や多様性を学べる絵本5選
友だちとの関わりが広がる小学校期。
違いを受け止めたり、自分らしさを楽しんだりできる絵本が心の支えになります。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
自己肯定感を高める・育む読み聞かせの工夫

絵本の読み聞かせは、物語を届けるだけでなく、子どもの心に安心を灯す時間です。
声のぬくもり、ことばの響き、ページをめくる音――すべてが「大切にされている」という実感につながります。
そんなひとときをより豊かにする、小さな工夫を紹介します。
📘読み聞かせのときの“声の出し方”や“集中をつくるコツ”は、【絵本の読み聞かせのコツ】で詳しく紹介しています。
読み聞かせ中は肯定的な言葉をそえる
「いいね」「わくわくするね」といった前向きな声かけを添えると、子どもは物語の世界をいっそう楽しめます。
たとえば主人公が新しいことに挑戦する場面で「ドキドキするね」と共感したり、笑えるシーンで「おもしろいね」と一緒に笑ったりすることも効果的です。
物語の展開に合わせて気持ちを言葉にすることで、子どもは安心しながらお話に入り込み、自分の感情を表現する練習にもなります。
こうしたやりとりの積み重ねが「大丈夫」「やってみよう」という気持ちをそっと支えてくれるのです。
読み終えた後に感想や質問を交わす
絵本を閉じたあと、「どの場面が好きだった?」「もし自分だったらどうする?」と問いかけてみると、子どもは心に残ったことを少しずつ言葉にしていきます。
たとえば、泣いている主人公を見て「かわいそう」と感じた子には「どんなときにそう思ったの?」とやさしく尋ねると、自分の気持ちを整理するきっかけになりまよ。
うまく言葉にできなくても、うなずいたり「そう思ったんだね」と受け止めたりするだけで十分です。
やりとりを通して「自分の考えを大切にしてもらえた」という実感が積み重なり、安心感や自己肯定感へとつながっていきます。
絵本時間を日々の習慣に
「さあ、お話の時間だよ」と声をかけ、寝る前に一冊読む。
そんな小さな決まりごとが、日々の安心につながります。
毎日ほんの数分でも、絵本を開く時間が生活のリズムに組み込まれると、子どもにとっては「大切にされている」と感じられる合図になります。
振り返れば、そのひとときはとても豊かで、親子にとって心を結ぶ習慣です。
本を開く時間は、家庭のなかでの安心基地。
そこで過ごすやわらかな時間が、日常の声かけや関わり方にも自然と温かさを広げていくでしょう。
司書と母の視点から伝えたい自己肯定感の大切さ
図書館で絵本を届ける現場と、家庭での子育て。
その両方を経験すると、読書が子どもの心にどのような支えとなるのかが見えてきます。
ここでは図書館で寄せられる声、家庭での体験、そして学びの節目に直面した場面を通じて、その意味を整理します。
日々多く寄せられる絵本にまつわる相談
「何歳からどんな絵本を読んであげればよいですか?」「5歳の子に合った本を探したいのですが」といった相談をよく受けます。
絵本とひとくちにいってもさまざまなジャンルやタイプがあり、皆さん迷ってしまうようです。
深くお尋ねし、年齢や発達段階に応じた数冊を紹介することも少なくありません。
一方で、日常の中では「うちの子は自信がなくて…」といった保護者の声も耳にします。
そうした不安に対して、絵本はすぐに解決をもたらすものではありませんが、心に残る小さなきっかけを届けることはできます。
時間をかけて種が芽吹くように、ゆっくりと支えになっていくのです。
子育て経験から見えた「繰り返し読み」の効用
子どもが「もう一回!」と同じ絵本を持ってくる姿は、とてもよくある光景です。
大人には単調に映っても、子どもにとっては安心できる展開を確かめたり、ことばのリズムを楽しんだりする大切な時間です。
「また?」と切り上げるのではなく、「いいよ、何度でも読もう」と受け止めることで、子どもは自分の気持ちを尊重されていると感じます。
そのやりとりの積み重ねが、「このままの自分でいいんだ」という感覚を静かに育てていくのだと、司書として多くのお子さんと接する中で実感しています。
自分を信じる力をそっと支えるアイテム
「できた」「もう一回やってみよう」——そんな小さな積み重ねが、子どもの自己肯定感を育てていきます。
遊びや生活の中で、自分の力を確かめながら前に進む感覚を持てることが大切です。
ここでは、挑戦と安心のバランスを支えてくれるアイテムを紹介します。
日々の中で“できた”を見つける時間を、親子で楽しんでくださいね。
自己肯定感を育む|つくって壊して、またつくる時間
三角と四角の組み合わせだけで“作れた”が増える設計。収納まで自分でやり切れると満足が長持ちしますね。
🎁 ボーネルンド|マグ・フォーマー ベーシック 62ピース(MF701007J)
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
細かな試行錯誤がそのまま形になる玩具。作例から自由制作へ移行しやすい中核セットです。
🎁 LaQ|ベーシック 511(収納ケース・650pcs+タイヤ等)
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
見える化で続けやすく|タイムタイマー&学習プランボード
色の面積で残り時間が見えると、区切りの切り替えが穏やか。自分のペースをつかみやすくなりますね。
🎁 Time Timer|MOD 60分(視覚タイマー)
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
一週間の予定と「できた」が一枚で完結。立てる・消すのリズムが心地よく、続けやすい設計が◎。
🎁 ソニック|リビガク マイプランボード(LV-4158-I/アイボリー)
価格・在庫はリンク先でご確認ください。
自己肯定感を育てる絵本時間のまとめ
絵本をひらく時間は、ただのお話の世界を楽しむだけでなく、子どもの心に安心や勇気をそっと灯すひとときです。
忙しい毎日のなかで数分でも読み聞かせができれば、家庭に「安心できる居場所」が生まれます。
その積み重ねが、自己肯定感という目に見えない大切な力を静かに育てていくのかもしれません。
年齢ごとの絵本選びを振り返る
乳児期には「愛されている安心感」を届ける絵本、幼児期には「挑戦や葛藤を乗り越える力」を描いた絵本、学童期には「個性や多様性を受け入れる視点」を育む絵本が心に響きます。
それぞれの時期に出会う一冊が、子どもの気持ちをやさしく支え、成長の節目で「大丈夫」という感覚を思い出させてくれるでしょう。
読み聞かせを続けるための小さな工夫
毎日同じ時間に短く読む、子どもに選ばせる、気に入った本を繰り返し読む――小さな工夫が習慣の土台になります。
やがて「また読んで!」という声が増え、その声に応える大人の姿勢自体が、子どもにとって「受け止めてもらえる安心」や「自分を認めてもらえる感覚」となって積み重なっていきます。
絵本1冊すべてを読めなくても大丈夫。疲れているときは「続きはまた明日」でもOKです。
読み聞かせは大人も子どももリラックスできる時間にしたいもの。
小さな約束は、絵本を読むひとときをより特別な時間にしてくれます。
関連記事でテーマをさらに広げる
「子どもの気持ちに寄り添う絵本」や「自信や挑戦する気持ちを育む絵本」、そして「年齢ごとのおすすめ絵本」など、関連テーマに目を向けてみるのもおすすめです。
📘関連ページもあわせてどうぞ。